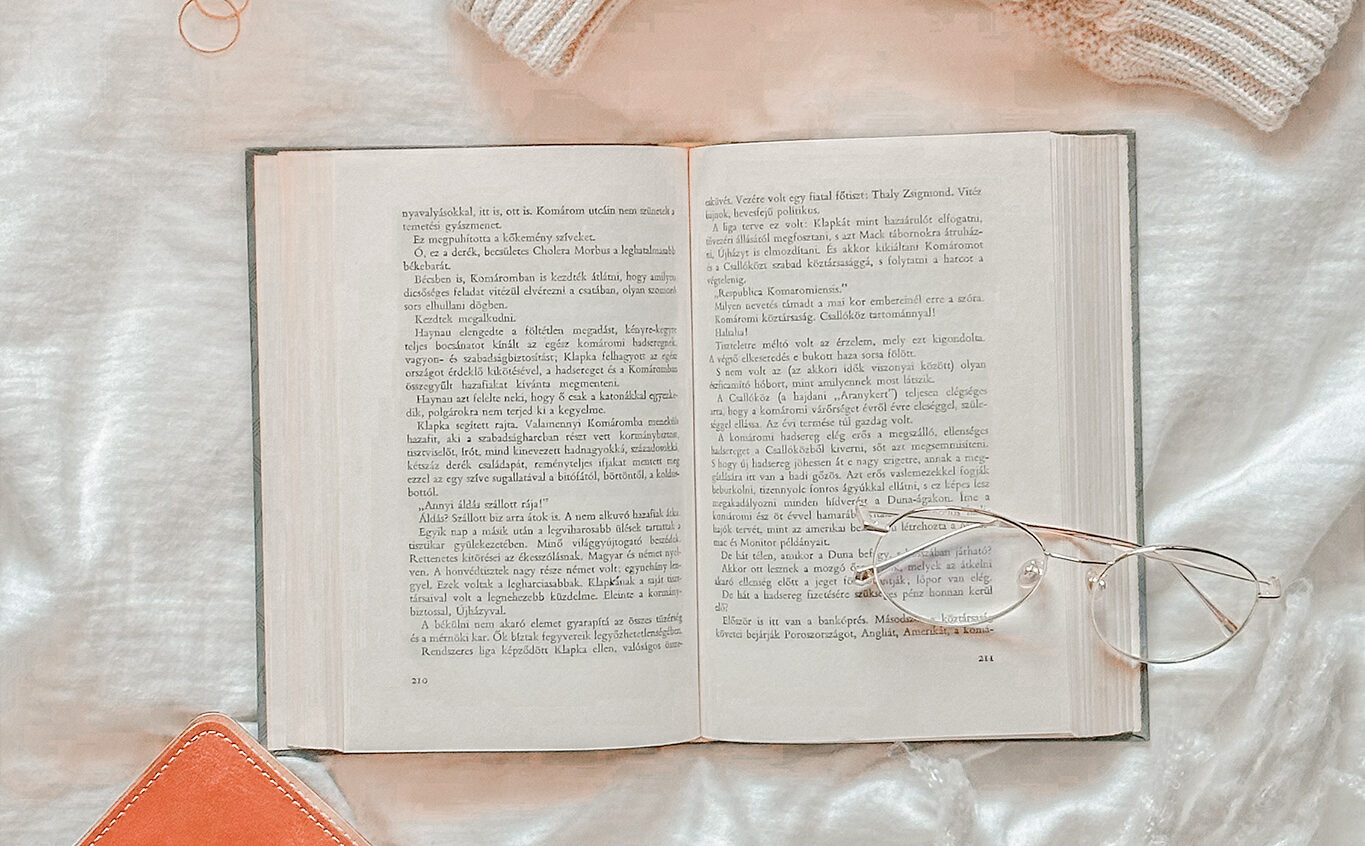座学というのは実はとても大事だと考えています。
退屈だなと考えがちですが、物事には道理というものがあります。
その道理を学ぶということは大事なことで、先人の知恵から学ぶのが座学の有意義なところだというのが個人的な立場です。
先人の知恵はパクっても怒られません。むしろしっかり盗んでください。
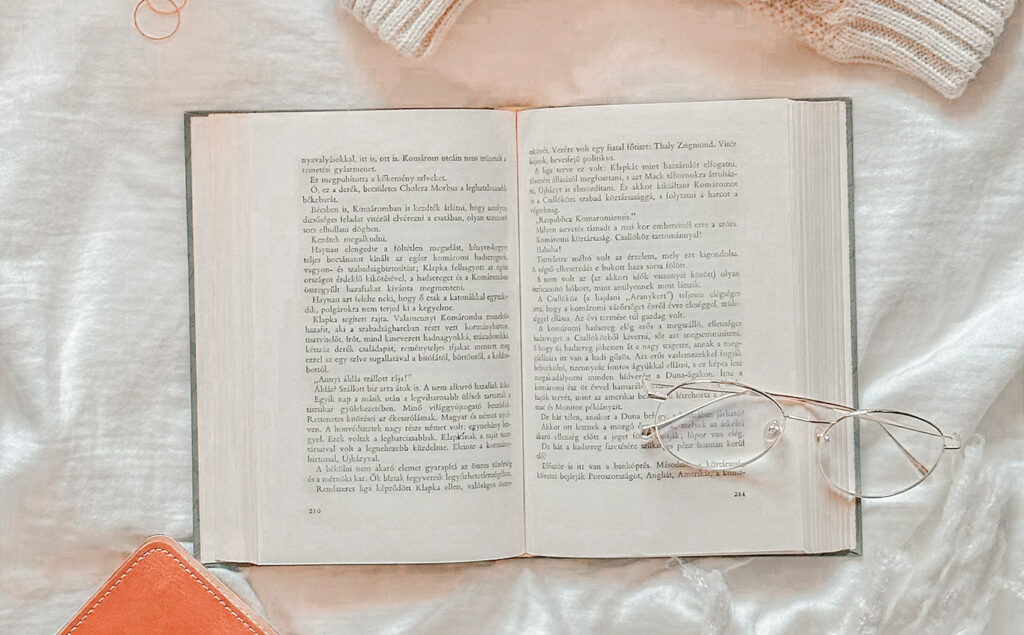
とはいえ、座学だけしていても意味がありません。
なにごとも血肉にするためには実践が必要だからです。
座学と実践、その両方があって初めて意味があります。
だから学んだことは実践しましょう。
やってみる。そこで何かしら得られるものは大きな意味を持ちます。
これはあくまでも私個人の考えではありますが、声の仕事というのはとても特殊な仕事だと考えています。
なにが特殊だと思いますか?
それは、声の仕事は未完成が前提だということが、です。未完成とは、ナレーター・声優その人がです。成果を数字で表現できないものの価値を表すことは非常に難しいです。ナレーター・声優の感性や技術、実力は数字では表せません。また、昨日より今日、今日より明日、より良くなっていて欲しいという願いもあります。だから演出をする側はより良いものを引き出そうと努力しますし、なんの経験もないタレントを事務所は売ることができるのです。期待・希望・想いを抱いているからです。
でも逆を言えば、未完成だからこそ今できる最善の努力をすることが求められるということでもあります。
努力をしろと言われてもなにをどう頑張ればいいのかわかりませんよね。だからこそ、日常の延長に学びを積み重ねて欲しいと思います。
ナレーター・声優の仕事というのは、日常の延長にあるんです。
あなたがなにげなくコミュニケーションをとっている相手、それが両親のときと、好きな異性や年上の誰か他人を相手にするとき、接し方は同じではありませんよね。
両親であればある程度気安く接することができるでしょう。
好きな異性であれば、その関係性にもよりますし、年上の誰かが相手では丁寧な言葉遣いをしたり、それ相応の礼儀をもって接するはずです。
これはおそらくほぼほぼ無意識に相手と自分の関係を察して行われることです。
これができることは当たり前だと思って、みんな深く考えませんね。
でも、無意識にこれができているということはすごいことなんです。
意識的にやれるということもすごいことです。
この相手と自分の関係性を考えて向き合うことは、相手への言葉遣いや態度、表情などのコミュニケーションを変える要素です。表現というのは「自分の内面をどのように表に出すか」だと思うのですが、それはすべて相手があってのことなんですね。
つまり、相手がいないのにする表現は独りよがりの妄想と同じで、相手がいて初めて表現というのは成立するものではないでしょうか。
相手に嫌われたくない、むしろ好かれたいとか。
相手に喜んで欲しい、良い印象をもってもらいたい、とかいろいろありますが、それらは相手がいて、その相手にどう自分を見せるかにつながることです。
ということは、芝居でもナレーションでもなんでも、相手がいなければ成立しない、ということではありませんか?
だから、どのような声が出せるか、どんな表現ができるかは、相手がいなければ何の意味もないんですね。相手がいなければすべて自己満足の域を出ません。
このあたりは芝居とはなにか、ナレーションとはなにかというような項目で今後もう少し詳しくお話をしたいと思いますが、日常生活の延長に学びを積み重ねて、それを意識的にできるようにすることが重要になってきます。
そして座学の大事なことですが、さきほど物事には道理があると書きました。その道理というのは、一面だけを見ていてはわからないことだらけです。
だれだれがこう言っていたからそうなんだ。そういう理解もありかもしれません。
でも大事なことは「なぜそうなのか」です。
コインには裏表があります。
でも、それを横から見る視点があると、コインはただの丸ではなくなります。当たり前だと思われがちですが、これがなかなか当たり前になっていません。物事をどのように見るのかの視点、それを学ぶのも座学があるかないかではそこに行きつくまでに差が出ることが多いものです。
先ほどコミュニケーションについて、「ほぼほぼ無意識に相手と自分の関係を察して行われること」と書きました。でもこれをより深く追求したとき、あなたの表現にはどれほどの引き出しが増えると思いますか?
その相手との関係、心の距離感や抱いている感情、相手にどう見られたいかなど日常生活で出会うたくさんの人との関係性を意識することが学生のうちから出来ていたら、芝居や表現にどれほどの深みにつながるのでしょうか。この文章をここまで頑張って読んだあなたには、新しい視点が加わっています。
これも座学の力です。なにも机に座って勉強するだけが座学ではありませんよね。
ひとつ視点の話として面白い例を挙げます。マクドナルドは皆さん知ってますよね。
マクドナルドの商売はなんだかわかりますか?
ハンバーガー屋に決まっている、そんな声が聞こえてきそうです。でも違うと言ったら、なにをしている会社なんだろうと思いますよね。
実は、マクドナルドは不動産屋です。少なくともそのように学びました。
何を言っているんだ、こいつは。そんな声が聞こえてきそうですが。
マクドナルドの出店計画というのは、いわゆる一等地と呼ばれる、不動産価値の高い場所を狙っています。すべてがそうではないとしても、基本的な出店計画は一等地を購入し、その支払いの手段としてハンバーガーを売っているというビジネスです。
これならば、なにかのきっかけでハンバーガーが売れなくなったとしても、その土地を使って商売ができるんですね。土地の売買もできれば賃貸とすることもできる。そのための一等地への出店計画です。だからハンバーガーは手段であって、目的ではないということになります。
経営者が変わったり、時代に合わせて企業文化に変化が出たりしますが、マクドナルドという会社のビジネスはもともと不動産を購入するための手段としてハンバーガーを売っていたと学びました。ハンバーガーを売ることが目的で、その効率のために不動産を購入している、だとしても結果的にハンバーガーを売ることだけが目的ではない、という意味で世界中にたくさんの不動産を持っている以上、不動産屋として見ることが妥当だと思います。
これが物事を見る視点の違いの例です。
このようにハンバーガーを売る会社だと決めつけてマクドナルドを見るのと、不動産屋としての側面からマクドナルドという会社を見るのでは、会社の理解にどれほどの違いが出るのかわかると思います。
日常からこのようにさまざまな視点で物事をとらえられると、なにか良いことがあるのかと言われそうですね。
芝居やナレーションの原稿と向き合うときにも役に立ちます。
自分の思考方法の癖にも気づくかもしれません。それは表現の狭さにつながりますから、その思考方法の癖、こういうときにこのように考えがちだ、という理解にもなります。そして、この視点があるとストレスが減ります。確実に減ります。
なぜなら、考え方の枠組みを変えることができるからです。
これを私は「フレームワークを変える」と言っていますが、自分の都合の良い、少なくともダメージの少ない解釈で物事を受け止めることができるようになります。
必要以上に落ち込むこともなくなるかもしれません。
悩むということに対しても、悩み方が変わります。
そして前向きに頑張ろうとしているときには、加速がついたりもします。
それらをここで並べ立てることはしませんが、先人の知恵を学ぶ座学はその捉え方次第では、道理を知るだけでなく、知識を見識にまで高めるもとになる素晴らしい教えに変わるかもしれません。だからこそ、少し意識してみることをおすすめしたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。