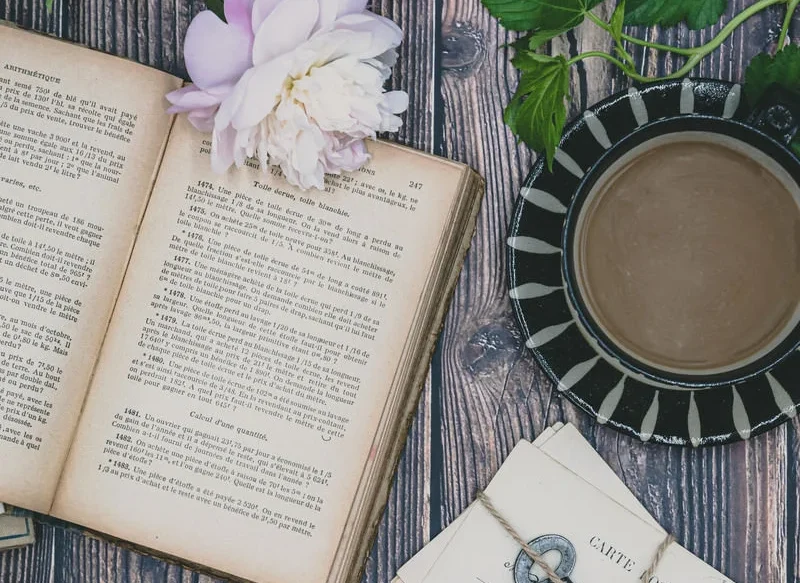ここではナレーション原稿との向かい方について考えてみようと思います。
ちょっと長いですが、あなたのナレーション力を確実に押し上げることのできる考え方を、できるだけ誰にでもわかるように、なるべく平易な言葉で書いたつもりです。

ナレーションの練習は、どんなやり方をしているのでしょうか。
色々な声色を使って読んでみるとか、どの言葉を立てて読むのかなどの、ただひたすら読む練習をしていませんか?
ナレーションがうまくなりたいなら、そもそもの考え方を変える必要があると思います。
まず考えることは、どのように原稿と向き合っているのか、です。
ナレーション原稿を前にして、口に出して読むまでに、あなたの脳内ではどのようなプロセスを経て読み始めますか?
原稿を読みながら内容を理解していく人もいれば、内容を理解してからどの言葉が大事なのかと考えて読む人もいるでしょう。内容を理解して、読みたいように読む人もいれば、頭が混乱してしまうのでなんとなく読む人もいそうです。
そういったやり方では、ナレーションはなかなかうまくなりません。
ではどのような考え方をしたら良いのでしょうか。
ここで、少し面倒でも何か書くものとノートを用意して、自分がどのような思考のプロセスを経て、声に出しているか書き出してみてください。
この作業をしてみると、これから学ぶ内容の理解がより深まると思うからです。
なにごとも現状を理解した上で、どう変わるかが大事です。
参考に、下記のように番号を振って、ひとつずつ書いていくとわかりやすいですね。
番号の数は例としてなので、人によってその数は多いかもしれませんし、少ないかもしれません。
①原稿の内容を理解する
②
③
④
⑤
→声に出して読む。
それでは、少し考えてみてください。書き終えてから読み進めることをおすすめします。

さて、書き出してみたでしょうか。
ここで一度考えなければいけないのは、今書き出してみた順番で毎回考えていますか、ということです。それを考えてみたら、案外同じ順番で考えているとは限らない、ということに気づくかもしれません。そう、つまり、その時の原稿の内容や気分、体調……そういったもので確たる考え方がない、ということも普通にありえます。
それはいいかえると、クオリティが担保されない、ということです。
原稿の内容や気分によってクオリティが担保されないということは、プロとしては致命的です。そんな人に仕事を任せられませんよね。
そこでここでは、原稿を前にしたときにどのように考えればよいか、について書いていきたいと思います。
まず原稿を前にしたら、内容を理解しなければなりません。わからない言葉の意味なども含めて、何が書かれているのか。だから、①は内容の理解ですね。伝えたいことはなにか、ということです。
①内容を理解する(伝えたいことはなにか)
そしてここからが大事です。その内容は誰に向けて書かれたものなのか、です。あるサービスについてや商品など、場合によっては企業のブランドイメージを上げるためのものであってもしても、その内容には対象となる相手がいます。
乳児用おむつを成人男性に売ろうとは思いませんし、高齢者向け女性用化粧品を十代の男性に売ることはないのです。
つまり、伝えたいことは、伝えたい相手がいることで成立します。
ここが案外抜け落ちます。こう書かれているからこう伝えたい、読みたい、そのように短絡的に反応してしまうんですね。考えて、ではなく反応してしまうんです。
なぜか。それは、そういう読み方を学んできているからです。場合によっては、なぜその読み方なのかではなく、このように読んだらいいという乱暴な指導もあります。
はい、そんなわけで、②で考えるべきことは、誰に伝えたいのか、です。
①内容を理解する(伝えたいことはなにか)
②その内容は誰に伝えたいのか
日常生活で、会話というものも同じですよね。
例えば、お腹が空いたから、お母さんに「ごはんまだ~?」とか聞くのも、ごはんを作ってくれるのがお母さんで、そのお母さんに伝えることが必要なのでそういう言葉を投げかけるわけです。
①お腹が空いたから、そろそろごはんをたべたい。
②作ってくれるのはお母さんだからお母さんに伝える。
こういうことですね。
はい、少し整理できてきました。伝えたい内容には伝えたい相手がいる。そこまでは押さえましたね。
ではここからさらに進んでいきます。
伝えたい内容を伝えたい相手に伝える、この次に必要になるのは、その内容を伝えたときに、相手にどんな感情を抱いてほしいか、です。
学校の友達でも先輩、先生や家族、相手は誰でもよいですが少し考えてみてください。
あなたが何かを伝えるときに、同級生と先生への言葉遣いは同じですか?
家族とお隣に住んでいるおじさんやおばさんでは同じ言葉遣いですか?
そう、違うんです。同じなわけないのです。
なぜでしょうか。
勘の良い方は気づいたと思います。
自分と相手との関係性がそれぞれ違うんですね。
自分と両親、兄弟と他人の誰か。それぞれ関係性が違うんです。そんなの当たり前だ、と言われそうですね。でも、ふだんあなたは無意識的に区別をして、態度や言葉遣いを変えているのが事実です。
例えば内申書に関わりそうな相手なら、悪く思われたくないから行儀よく接してみるとか、お父さんとか別に何とも思っていないから気を遣うこともないと考えてみたり、友達だからこのくらいまでは許してくれるかな、みたいな考え方を無意識的に区別して態度や言葉遣いを変えているんです。
この事実をしっかり受け止めてください。
相手との関係性で態度や言葉遣いを変えているということは、その相手に合わせて「どう感じてほしいか」「どんな行動をしてほしいのか」というようなことを考えているということです。
これは当たり前のように思えて、経験則からくる行動です。
原稿には、伝えたい内容と伝えたい相手がいる、と書きました。
そうであるならば、その相手にその内容を伝えたときに、「どんな気持ちになってほしいのか」を考える必要があります。だって、その目的があるから、伝えるべき内容を伝えるべき相手に伝えたいのですから。はい、そういうわけで③は伝えたときにどんな気持ちや考えになってほしいかを考える、です。
①内容を理解する(伝えたいことはなにか)
②その内容は誰に伝えたいのか
③相手に伝えたときにどんな感情・考えをもってほしいのか
原稿を前にしたときに、日常生活で誰かと接するときに無意識的にやっている行動を、意識的に考える必要があります。ここまでくると、④は③の感情・考えを持ってもらうために「どう伝えるか」となります。ここまで考えて、はじめてどう伝えるか、なんですね。
①内容を理解する(伝えたいことはなにか)
②その内容は誰に伝えたいのか
③相手に伝えたときにどんな感情・考えをもってほしいのか
④そのためにどのように伝えるか
立てるべき大事な言葉を探すとか、読みの雰囲気を考えるとか、映像を頭にイメージするとか、人によってそれぞれあるでしょうけれど、本質は日常生活で行っていることの意識化が大事だということです。
このようにして考えていくと、ナレーションには「はずれはあるけれど正解はない」ということになります。野球のストライクゾーンのように、ある程度の枠内に収まればひとまずOKということです。ただし枠から出てしまえばはずれです。的外れ、ということになります。
センスという言葉を使いたがる業界でもありますが、センスというのはどのように伝えるか、まで来て初めて問われるものではないでしょうか。
「どんな伝え方をしたらより良いのか」も結局のところ、どれだけ相手のことを考えて日常生活を送ってきているか、ということの積み重ね、経験が大きいと思います。
どんなふうに読みたい、どんな読み方ができる、はしょせん「自分勝手」でしかありません。
自分勝手な読み方をしているから、うまくなれないんですね。そしてその読み方には一貫した考え方がないので、原稿の内容にクオリティが左右されてしまう。
うまくいったときは、たまたま、あくまでも偶然良かっただけという練習では、効果はなかなかでませんよね。
今一度、考えてみることをおすすめします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
もう少し踏み込んだ内容は【③声優として活躍したい】のほうで公開予定です。このブログでは少しでも役に立てると思うことをマネジメントをしている立場から書いていきたいと思っています。
そして、二本柳凛というペンネームでNOTEというブログサイトに小説を公開しています。
小説仕立てではありますが、今回書いたような内容を物語として学べるように頑張って書きました。
よろしければ目を通してみてください。
俺は訳あって声優になりたい奴の手伝いをしなければいけなくなった